2025.07.29
営業代行は効果ない?うまく活用するコツや利用すべき企業の特徴も解説
「営業代行って本当に効果あるの?うちには合わない気がする…」
「実際にお願いしたけど成果が出なかったって話も聞くし不安…」
営業代行の導入を検討しているものの、「効果がないのでは?」という疑念や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論、営業代行が効果を発揮するかどうかは、依頼先の選定と活用方法次第です。間違った選び方や運用では、効果なしとなってしまうケースもあります。
本記事では、営業代行が「効果ない」と言われる理由や成果につなげるためのポイント、などを詳しく解説していきます。
売上停滞や営業課題を根本から見直したいなら、EachWorthの営業支援がおすすめです。戦略設計から組織づくりまで、成果につながる再現性ある体制を構築します。
営業代行が「効果ない」と言われる理由
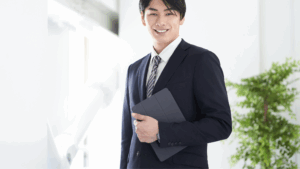
営業代行を導入しても「成果が出ない」「想定と違う」と感じる企業は少なくありません。
主な理由は以下の通りです。
・業務内容が不透明
・ターゲット選定の精度が低い
・コストが成果に見合わない
・商材理解が浅く訴求力が弱い
詳しく解説します。
業務内容が不透明
営業代行に業務を委託する際に多くの企業が直面するのが、実際にどのような営業活動が行われているかが見えにくいという問題です。
たとえば「どれだけ架電したか」「どういったトークをしているのか」「なぜ失注したのか」など、進捗や品質を把握する手段がなければ、改善の糸口もつかめません。
このようなブラックボックス状態では、仮に成果が出たとしても再現性のある学びは得られず、社内にノウハウも蓄積されません。
結果として、「結局何がどう効果的だったのかわからない」という状況に陥ってしまいます。
営業代行の内容を定期的に可視化し、レポートや打ち合わせを通じて透明性を確保することが必要です。
ターゲット選定の精度が低い
営業活動において、誰にアプローチするかは重要です。
しかし、営業代行が事前に十分な市場調査や自社とのディスカッションを行わずに、一律のリストに対して営業をかけてしまうと、成果につながる可能性は大きく下がります。
特にBtoB商材の場合、ターゲット企業の業種、規模、課題感といった属性に応じた訴求が求められます。
ターゲットがずれていれば、どれだけ優れた営業トークを用いても成果は出ません。
営業代行に任せきりにするのではなく、自社側もペルソナ設計や顧客リストの精査に積極的に関与することが、精度の高い営業活動につながります。
コストが成果に見合わない
営業代行の費用対効果に疑問を持つ企業は多く、特に「費用は支払ったが、商談や成約が取れなかった」といったケースでは、「効果がない」と判断されがちです。
これは単に営業代行が悪いというより、費用体系と成果指標のミスマッチが原因であることが少なくありません。
たとえば、アポイント件数に対する従量課金型の契約であっても、質の低いアポばかりが増えれば意味がないのです。
コストと成果を正確に結びつけるためには、成果の定義(例:商談化率、受注確度など)を明確にし、契約前にその点を合意しておくことが必要です。
商材理解が浅く訴求力が弱い
営業代行は自社の社員ではないため、どうしても商材への理解が浅くなる傾向があります。
その結果、顧客の課題に対して適切な訴求ができず、「なんとなく話を聞いただけで終わってしまった」となることも出てきます。
特に専門性が高いサービスや商品を扱う業界では、基本的な商品知識だけでなく、市場の構造や顧客のニーズに深く精通していなければ成果は出にくいです。
営業代行と契約する際には、導入前研修や定期的な情報共有の場を設け、商材理解を深める取り組みを怠らないことが重要です。
営業代行を効果的に活用するコツ

「効果がない」と感じてしまう原因を避けるためには、営業代行の使い方そのものを見直すことが大切です。以下では成功に導く3つのコツを解説します。
目的とKPIを明確に設定する
営業代行を活用する際には、まず「何のために利用するのか」を明確に定めることが前提です。
新規リードの創出、既存顧客の深耕、テストマーケティングなど、目的が曖昧なままでは施策がブレてしまい、成果を正しく測ることができません。
また、目標設定においても、「月に〇件の商談」「アポからの成約率〇%」など具体的なKPIを共有し、営業代行と同じ目線で進めることが求められます。
これにより、期待と現実のギャップを最小限に抑え、費用対効果の高い施策につなげることができるでしょう。
自社との連携体制を強化する
営業代行にすべてを丸投げしてしまうと、現場の状況が見えなくなり、改善点にも気づけません。
成果を出すためには、自社と営業代行との密な連携が欠かせません。
たとえば、週次・月次での定例ミーティングを設け、活動内容や顧客の反応、課題などを共有する仕組みが必要です。
また、現場の声を迅速にフィードバックし、スクリプトやターゲット選定に反映させていくことで、精度の高い営業活動ができるようになります。
営業代行を外注先ではなく、共に成果を出すパートナーと捉える姿勢が重要です。
商材・市場に強いパートナーを選ぶ
営業代行会社にも得意不得意があるため、自社の商材や市場に精通しているパートナーを選定することが成功の鍵です。
たとえばITサービスに強い会社もあれば、製造業や不動産などに特化している会社もあります。
自社の業界やターゲット層への理解が深いパートナーを選ぶことで、訴求力のある営業トークが可能となり、成果も出やすくなります。
過去の実績や対応業界、スタッフの知識レベルなどを事前に確認し、営業力だけでなく相性の良さも見極めることが大切です。
営業代行を利用すべき企業

営業代行を利用すべき企業は、主に以下3つに該当する企業です。
・営業リソースが不足しているスタートアップや中小企業
・テストマーケティングを行いたい企業
・営業ノウハウを蓄積したい企業
詳しく解説します。
営業リソースが不足しているスタートアップや中小企業
人手が限られており営業活動に十分な時間やマンパワーを割けないスタートアップや中小企業にとって、営業代行は強力な支援手段になります。
特に新規開拓に注力したいが、社内に経験者がいない、もしくは手が回らないという場合には即効性のある選択肢です。
自社では難しいエリアや業界へのアプローチも可能となり、機会損失を防ぐことができます。
ただし、依頼内容や期待値を明確にしておくことで、無駄なコストを抑えつつ成果につなげることができます。
テストマーケティングを行いたい企業
新サービスや新市場への参入を検討している企業が営業代行を利用することで、スピーディーに市場反応を得られます。
自社でリサーチから営業までを一貫して行うには時間とコストがかかりますが、営業代行を活用すれば短期間で有益なデータを収集できる点が魅力です。
たとえば、ターゲットごとの反応、競合他社との比較、訴求内容の改善点などを把握することで、今後の戦略立案にも役立ちます。
仮説検証型の営業活動には、営業代行の柔軟性がマッチしやすいです。
営業ノウハウを蓄積したい企業
営業代行は単なる外注ではなく、自社の営業ノウハウを蓄積する手段としても活用できます。
定例報告や商談内容の共有を通じて、どんなアプローチが成果につながったのかを学ぶことで、社内の営業体制の強化にもつなげられます。
特にこれからインサイドセールスやマーケティング部門を立ち上げようと考えている企業にとっては、実務から得られる知見は貴重です。
営業代行から得られる情報を自社の資産として活かす意識が、長期的な成長を促します。
まとめ:営業代行の特性を理解し自社に合った戦略を描こう
営業代行が「効果ない」と言われてしまう背景には、パートナーの選定ミスや、活用方法の誤りといった課題が潜んでいます。
外部リソースに頼る以上、自社との連携や目的の明確化が欠かせません。また、代行業者選びでは業界への理解や実績も重視すべきです。
営業代行はあくまで手段であり、戦略的に活用すれば大きな成果を生む可能性を秘めています。この記事を参考に、自社の状況に合った活用方法を見極めていきましょう。
売上停滞や営業課題を根本から見直したいなら、EachWorthの営業支援がおすすめです。戦略設計から組織づくりまで、成果につながる再現性ある体制を構築します。
