2025.07.08
顧客リストの作り方と具体的な活用方法|管理方法も徹底解説
「営業先が思うように増えない…」
「効率的に売上につながる顧客リストを作りたい」
そう思う方もいるのではないでしょうか。
顧客リストは、売上を伸ばすための土台です。ただやみくもに情報を集めるのではなく、戦略的にリストを作ることで、営業やマーケティングの精度が格段に上がります。
本記事では、そもそも顧客リストがなぜ重要なのかを解説した上で、具体的な顧客リストの作り方や注意点、実際の活用方法まで詳しくご紹介していきます。
EachWorthは、営業設計から実行・改善まで伴走し、継続的に「売れる仕組み」を構築いたします。採用に頼らず営業組織を強化したい企業様は、ぜひ以下からご相談ください。
顧客リストの必要性

営業や販促活動の成果を最大化するためには、質の高い顧客リストの整備が必要です。顧客リストの主な必要性は以下の通りです。
・営業活動の効率化が図れる
・継続的な販促・リピート獲得の土台になる
詳しく解説します。
営業活動の効率化が図れる
営業活動では誰にアプローチするかを明確にすることが成果の鍵を握ります。
顧客リストがあることで、過去の取引履歴や関心のある商品・サービスなどを把握しやすくなり、相手に合わせた提案が可能です。
特に訪問営業や電話営業など、直接的なコミュニケーションが必要な場合、事前に情報が揃っていることでアプローチの無駄を減らせます。
また、営業の進捗状況を記録しやすくなり、チーム全体での共有も容易になります。これにより、属人的な営業から脱却し、仕組み化された営業体制を構築できるようになるでしょう。
継続的な販促・リピート獲得の土台になる
顧客リストを活用することで、一度取引があった顧客に対して定期的なフォローや情報発信が可能です。
たとえば、キャンペーン情報や新商品の案内をタイミングよく送ることで、リピート購入を促進できます。
また、過去の購買履歴をもとに顧客ごとのニーズを予測し、個別対応を強化することも可能です。
これにより、長期的な関係性を築きながら、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつなげることができるでしょう。
ゼロから始める顧客リストの作り方

これから顧客リストを作ろうとする方にとって、最初にすべきは「目的に応じた正しい手順の理解」です。
ここでは、ゼロから始める場合の具体的な作成ステップを順を追って解説します。
ターゲットを明確にする
最初のステップは、どのような顧客をリストに含めるかを定義することです。
性別・年齢・職業・地域といった基本的な属性に加えて、購買意欲やニーズの深さなども検討対象にします。
ターゲット像を具体化することで、集める情報の内容や営業方針にも一貫性が生まれます。
ターゲットが明確でないと、無関係な情報を集めてしまい、リストの精度が低下する原因となるでしょう。
ペルソナを設定し、目的に沿った顧客層に焦点を絞ることが、効率的なリスト作成につながります。
情報収集の手段を決める
次に、顧客情報をどのようにして集めるかを決定します。
店舗での会話、問い合わせフォーム、展示会、SNS、アンケート、セミナーなど、収集方法は多岐にわたります。自社のビジネスモデルに適した手段を選ぶことが重要です。
たとえば、BtoBであれば名刺交換や問い合わせ経由の情報が中心となりますし、BtoCであればSNSフォロワーやメルマガ登録者が対象になることもあります。
情報の取得元を明確にしておくことで、後の管理もしやすくなるでしょう。
顧客情報に必要な項目を定義する
顧客リストには、氏名や連絡先といった基本情報に加えて、自社の営業活動に有益な情報を加えることが求められます。
たとえば、過去の購入履歴、関心のある商品カテゴリ、問い合わせ内容、来店頻度などが挙げられます。
必要以上に情報を集めても管理が煩雑になるため、目的に沿って収集すべき項目を事前に定義しておくことがポイントです。
また、入力形式(例:電話番号のハイフンの有無など)を統一しておくことで、リストの整合性も保ちやすくなります。
スプレッドシートやCRMに整理して入力する
収集した情報は、スプレッドシートやCRM(顧客管理システム)などに整理して入力します。
手軽に始めたい場合はGoogleスプレッドシートが便利ですが、中長期的な活用を見据えるならCRMの導入も視野に入れるべきです。
入力時には、誤記を防ぐためのチェック体制や入力ルールの策定が必要です。
また、検索やソートがしやすいように、項目ごとに列を分け、正規化された形式で記録していく必要があるでしょう。
セグメント分けとスコアリングで優先順位をつける
作成した顧客リストは、そのまま使うのではなく、顧客の特徴や見込み度に応じてセグメント分けを行いましょう。
たとえば「新規」「リピーター」「高LTV」「クレーム対応済」などの分類が該当します。
さらに、スコアリングを導入することで、営業優先順位を明確にできます。スコアの基準は、直近の接点回数、反応率、購買履歴などを加味して設計します。
こうしたセグメントとスコアを活用することで、的確なアプローチが可能です。
作成した顧客リストの具体的な活用方法

顧客リストは作るだけでは意味がなく、実際にどのように使うかが成果を大きく左右します。ここでは、作成したリストを使った営業・販促の具体的な活用法を解説します。
顧客の見込み度に応じたアプローチ手法を使い分ける
顧客リストをもとに、見込み度に応じてアプローチの手法を変えることで、反応率と成約率を高められます。
たとえば、見込み度の高い顧客には個別対応や訪問営業を、見込み度の低い顧客には情報提供型のメールマーケティングを行うなど、段階的なアプローチが効果的です。
また、スコアリングによって「今すぐ客」「そのうち客」「情報収集中」などに分類し、それぞれに合った接触頻度や内容を調整することで、効率的に商談化やリピート化へと導けます。
メール・LINE・電話・DMなどチャネルごとに最適化する
同じ情報でも、伝えるチャネルによって届き方や反応が大きく異なります。顧客ごとに好まれる連絡手段が異なるため、チャネルを最適化することが重要です。
たとえば、若年層にはLINEやSNS、高齢層には電話やハガキDMといった使い分けが効果的です。
チャネルごとにテンプレートや配信スケジュールを整備し、適切なタイミングで適切な情報を届けることで、コミュニケーションの質を高められます。
結果、顧客満足度や成約率の向上につなげることができるでしょう。
リストをもとに販促スケジュールを決める
顧客リストに基づいて販促の年間スケジュールを設計することにより、計画的かつ戦略的なプロモーション活動が可能です。
たとえば、誕生日や記念日、購入からの経過日数などを活用し、タイミングを見計らったフォローができます。
また、セールやイベントの告知を事前にリストに基づいてセグメント配信すれば、より関心の高い層に集中して情報を届けられます。
これにより、無駄なコストを削減しながら販促効果を最大化できるでしょう。
作成した顧客リストの管理方法
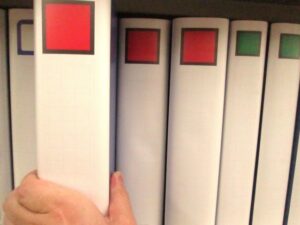
作成した顧客リストは、主に以下の方法で管理しましょう。
・定期的に情報を更新する
・CRMやスプレッドシートを活用して一元管理する
・社内での共有ルールとアクセス権限を明確にする
詳しく解説します。
定期的に情報を更新する
顧客情報は時間とともに変化します。電話番号やメールアドレスの変更、担当者の異動、会社の移転などにより、古い情報のままではアプローチが無駄になるリスクがあります。
そのため、定期的な情報の見直しと更新が大切です。
更新のタイミングとしては、半年ごとや年1回などルールを決めて一斉確認を行う方法が一般的です。
また、営業活動や問い合わせのタイミングで情報の確認・更新を習慣化することで、常に最新の状態を保つことができます。
CRMやスプレッドシートを活用して一元管理する
顧客情報は部署ごとにバラバラに管理されがちですが、一元管理されていないと重複や漏れ、矛盾が発生しやすくなります。
そのため、CRMツールや共有のスプレッドシートを活用し、社内で統一されたフォーマットで管理することが重要です。
一元管理することで、社内の誰でも必要なときに必要な情報を迅速に取得でき、営業活動やサポート対応の質が向上します。
特にCRMでは履歴やステータスの可視化ができるため、顧客対応の属人化を防ぎ、チームでの連携も強化されるでしょう。
社内での共有ルールとアクセス権限を明確にする
顧客リストは営業部門だけでなく、マーケティングやカスタマーサポートなど、複数の部署で共有されることが多いため、ルール作りが重要です。
たとえば、誰がどの項目を編集できるか、履歴はどう残すか、バックアップ体制はどうするかなど、あらかじめ定めておく必要があります。
また、機密性の高い情報も含まれるため、アクセス権限を設定し、必要な人だけが閲覧・編集できるようにすることで、情報漏えいや誤操作のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
まとめ|営業成果につなげるには作り方と活かし方の両立が重要
顧客リストは単なる名簿ではなく、営業や販促の精度を高めるための重要な資産です。
精度の高い顧客リストを作成するためには、明確なターゲット設定から情報の収集・整理・分類に至るまでの手順を丁寧に実行する必要があります。
継続的な成果を上げるためにも、作るだけでなく、活かし、守るという視点を持つことが重要です。
EachWorthは、営業設計から実行・改善まで伴走し、継続的に「売れる仕組み」を構築いたします。採用に頼らず営業組織を強化したい企業様は、ぜひ以下からご相談ください。
