2025.07.08
営業代行会社の選び方5選|おすすめの乗り換え検討時期や注意点などを解説
「営業代行ってどうやって選べばいいの?基準がわからない」
「信頼できる営業代行会社に乗り換えたいけど、失敗したくない…」
そう思う方もいるのではないでしょうか。
営業代行を依頼しても、成果が出なかったり、連携がうまく取れなかったりするケースは少なくありません。
だからこそ、自社の営業戦略に合った代行会社を選ぶには、「営業スタイルとの相性」や「得意業界」「対応範囲」「契約条件」など、いくつかの明確な基準をもとに比較検討することが大切です。
本記事では、営業代行の選び方について、見極めのポイントや業者ごとの違い、注意すべきことなど詳しく解説します。
売上停滞や営業課題を根本から見直したいなら、EachWorthの営業支援がおすすめです。戦略設計から組織づくりまで、成果につながる再現性ある体制を構築します。
営業代行会社のを乗り換え検討するべきタイミング
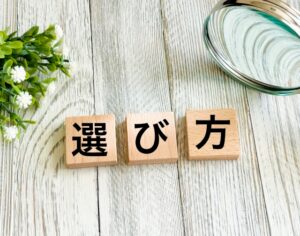
営業代行をすでに利用している企業であっても、すべてのケースで満足のいく結果が出るとは限りません。
ここからは、営業代行会社のを乗り換え検討するべきタイミングを詳しく解説します。
コミュニケーションにストレスやズレを感じるようになった
営業代行会社とのやり取りにおいて、報告が遅かったりレスポンスが悪かったり、依頼した内容と実際の活動がズレていると感じるようになった場合は乗り換え検討するべきです。
営業代行は単なる作業外注ではなく、顧客接点を担うパートナーである以上、密なコミュニケーションと信頼関係が前提になります。
報連相が不足すると、戦略上のすれ違いや無駄な工数が発生し、最終的には成果にも影響を及ぼすでしょう。
このようなストレスが慢性化している場合は、別の代行会社への切り替えを前向きに検討してください。
成果が出ない状態が3ヶ月以上続いている
営業代行を導入しても、明確な成果が3ヶ月以上見られない場合は、現状の代行会社に課題がある可能性があります。
営業活動には一定の立ち上がり期間が必要ですが、成果の兆しすら見えない状況が続くのは問題です。
とくにKPIが明確に設定されているにもかかわらず未達が続くようであれば、営業手法や対応力に問題があると考えられます。
改善の兆しがない場合は、思い切って他の業者に切り替えることで、新たなアプローチや仕組みが成果に結びつく可能性も広がります。
自社の営業戦略が変わり現行の代行会社とズレが生じた
市場環境や事業フェーズの変化により、自社の営業戦略を見直した結果、現行の営業代行会社の得意領域とズレが生じてしまうことがあります。
たとえば、従来はBtoC向けだったのがBtoBにシフトした、単価の高いコンサル型商材を扱うようになったなどの変化です。
このような場合、代行会社が過去の手法に固執して対応できないと、成長の足かせになりかねません。
戦略の転換期には、改めて自社の方向性にマッチしたパートナーを再選定することが重要です。
営業代行会社の種類

営業代行会社にはさまざまな種類があり、それぞれ強みや対応領域が異なります。ここからは、具体的な営業代行会社の種類をご紹介します。
インサイドセールス型の営業代行会社
インサイドセールス型は、電話やメール、オンライン会議ツールを活用して、非対面で営業活動を行うスタイルの代行会社です。
見込み顧客の育成(ナーチャリング)から商談化までを担うことが多く、特にBtoB商材や検討期間の長い商材に向いています。
マーケティング部門と連携しながらリード獲得〜育成までを一気通貫で担うことができるため、営業の仕組みづくりに課題を感じている企業にも適しています。
フィールドセールス(訪問営業)型の営業代行会社
フィールドセールス型は、営業担当者が顧客先を訪問し、対面でヒアリング・提案・クロージングを行うスタイルです。
顧客ごとの課題に深く入り込む必要がある高単価商材や、信頼関係の構築が重視される業種に向いています。
代行会社の担当者のスキルに大きく成果が左右されるため、過去の実績や営業スタイルの確認が重要になります。より濃い関係構築を目指す企業にとっては有力な選択肢です。
テレアポ代行型の営業代行会社
テレアポ代行型は、電話でのアポイント獲得に特化した営業代行会社です。新規開拓のためのリード獲得に強みがあり、短期間で多くの接点をつくることが可能です。
ただし、商談後のクロージングや顧客育成には関与しないケースが多いため、自社でその後の営業体制を整えておく必要があります。
効率的に商談の入り口を増やしたい企業に適しているでしょう。
営業代行会社の選び方

営業代行会社の選び方は、主に以下の通りです。
・営業スタイルと得意業界のマッチ度を確認する
・対応範囲を明確にする
・過去の実績・クライアント事例をチェックする
・担当者との相性・コミュニケーション体制を見極める
・柔軟な対応ができる運用体制かどうかを見極める
詳しく解説します。
営業スタイルと得意業界のマッチ度を確認する
営業代行会社ごとに得意な営業スタイルや業界が異なります。
自社がBtoB向けの高単価商材を扱っている場合、インサイドセールスに強い業者が適している可能性があり、地域密着の店舗ビジネスであればフィールドセールス型の業者が合うかもしれません。
相手がこれまでどのような企業と取引してきたか、どのような実績があるかを確認し、自社のビジネスモデルに適した営業手法を提供できるかを見極めることが重要です。
対応範囲を明確にする
営業代行と一口に言っても、対応範囲には大きな差があります。
たとえば、テレアポのみの支援なのか、商談〜クロージングまで一貫して行うのかなど、業務領域は業者によって異なります。
契約前には必ず、どこまでの範囲を対応してくれるのかを明確にし、自社の営業体制の中で何を補完してもらうのかを整理しておくことが大切です。
過去の実績・クライアント事例をチェックする
信頼性のある営業代行会社かどうかを判断するためには、過去の取引実績やクライアントの事例を確認することが効果的です。
どのような業界・企業規模の支援をしてきたのか、どのようなKPIを設定し、どの程度の成果を出してきたのかなど、具体的な数値を確認できる資料があると安心です。
また、可能であれば実際の顧客の声やレビューもチェックし、現場での評価を把握するようにしましょう。
担当者との相性・コミュニケーション体制を見極める
営業代行会社と成果を出すには、担当者との信頼関係と綿密な連携が欠かせません。
報連相の頻度、商談のフィードバックの質、改善提案の積極性など、コミュニケーション体制を事前にチェックしておきましょう。
また、初回打ち合わせの段階で「この担当者とスムーズにやり取りできそうか」という感覚的な相性も大切な判断材料です。
実務が始まってからのやり直しは難しいため、契約前の擦り合わせを丁寧に行うことが成功のカギとなるでしょう。
柔軟な対応ができる運用体制かどうかを見極める
営業活動は日々変化するものであり、状況に応じた柔軟な対応力が求められます。
そのため、マニュアル通りの営業しかできない代行会社では、突発的な課題や戦略変更に対応できない恐れがあります。
提案や改善を自発的に行ってくれるか、週次や月次でPDCAを回す体制があるかなど、運用の柔軟性と主体性を見極めることが大切です。
営業代行を選ぶ際に注意すべきポイント

営業代行を選ぶ際に注意すべきポイントは、主に以下の通りです。
・契約内容・期間・解約条件を必ず確認する
・アポ獲得数=成果ではないことに注意
・トライアル契約や少額スタートができるか
詳しく解説します。
契約内容・期間・解約条件を必ず確認する
営業代行サービスの契約は、内容や期間によって柔軟性が大きく異なります。
たとえば、最低契約期間が設けられている場合、途中で成果が出ないと判断してもすぐには解約できない可能性があります。
また、解約時に違約金が発生する契約も存在するため、事前に条件を十分に確認しておくことが必要です。
営業活動は成果が出るまでに時間がかかることも多いため、万が一のリスクも視野に入れて契約条件を慎重に見極めましょう。
アポ獲得数=成果ではないことに注意
営業代行会社によっては、アポイント獲得数だけを成果指標とするケースがあります。
しかし、単にアポが取れたとしても、それが自社の理想的な見込み客でなければ意味がありません。
たとえば、商談の質が低かったり、成約見込みが極めて低いアポばかりでは、実質的な売上には結びつかないのです。
そのため、契約前に「どのようなアポが質の高いリードなのか」を営業代行会社とすり合わせておくことが重要です。
トライアル契約や少額スタートができるか
いきなり本契約を結ぶのではなく、一定期間のトライアル契約や少額スタートを受け入れている営業代行会社であれば、サービスの質を見極めやすくなります。
実際に稼働してもらうことで、営業手法や報告体制、担当者との相性などを把握することができ、リスクを抑えて本契約に進む判断が可能です。
慎重にパートナー選定を行いたい企業にとっては、このような柔軟な契約スタイルが用意されているかを確認することも重要なポイントです。
まとめ
営業代行会社を選ぶ際には、営業スタイルや得意業界、対応範囲、実績、契約条件など、複数の観点から総合的に判断することが求められます。
また、選定後も継続的なコミュニケーションを通じて信頼関係を構築し、成果につなげるための協力体制を整えることが重要です。
売上停滞や営業課題を根本から見直したいなら、EachWorthの営業支援がおすすめです。戦略設計から組織づくりまで、成果につながる再現性ある体制を構築します。
